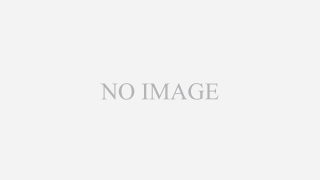日本経済の没落原因は為替政策にあり
高度経済成長後、日本経済が没落した原因は「為替政策」にある。
日本の経済成長は、かつて1ドル=360円という「超円安」の恩恵によって可能だった。
1971年のニクソン・ショックで固定相場制が終わり、「ダーティーフロート(管理変動相場制)」に移行。
日本政府・財務省は資本移動を制限することで、円安状態を維持していた。
この状態にアメリカが不満を持ち、日米摩擦が深刻化し、1985年の「プラザ合意」へとつながった。
プラザ合意で資本移動が自由化され、為替は理論値に向かって円高が進行。
日本政府・日銀は、1971年〜1985年の間に段階的に理論値に近づけるチャンスがあったが、それを怠った。
その結果、日本は「下駄を履かされた状態(優遇された円安環境)」から「裸で勝負」せざるを得なくなり、競争力を失った。
その失策の「戦犯」は、大蔵省(現財務省)である。
さらに、失敗の帳尻を合わせようと消費税導入などを行い、二重の失策になった。