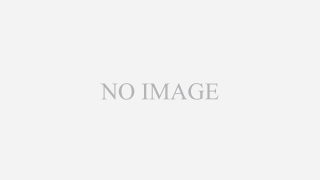あこがれの軽井沢の歴史
-
江戸時代の繁栄:
-
軽井沢宿は、碓氷峠の西側に位置し、峠を越える旅人にとって重要な休息地でした。碓氷峠は中山道有数の難所で、軽井沢宿はその入口として交通・軍事上の要衝でした。
-
天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によると、宿内家数は119軒(本陣1軒、脇本陣4軒、旅籠21軒)、人口は451人で、最盛期には旅籠が100軒近くあり、数百人の飯盛女(旅人に食事を提供する女性)が働いていました。
-
宿場の北端にある「二手橋」は、旅人と飯盛女が別れを惜しむ場所として知られていました。
-
しかし、浅間山の噴火(特に天明3年・1783年の大噴火)による火山灰や土石流で甚大な被害を受け、宿場の家屋や農作物が壊滅するなど、自然災害にも見舞われました。
-
軽井沢宿は、隣接する沓掛宿(中軽井沢)、追分宿(信濃追分)とともに「浅間三宿」と呼ばれ、参勤交代や旅人で賑わいました。追分宿は北国街道との分岐点でもあり、軽井沢宿を含むこの地域は経済的に活況を呈していました。
-
-
明治以降の衰退:
-
明治時代に入り、参勤交代の廃止や鉄道・新しい道路(明治17年の碓氷新道開通)の整備により、中山道の交通量が減少し、軽井沢宿を含む宿場町は衰退しました。
-
洪水や火災、開発により、軽井沢宿や沓掛宿の江戸時代の町並みはほぼ失われ、現在は旧軽井沢銀座周辺にわずかな面影が残るのみです。一方、追分宿は一部の町並みや史料が残り、往時の様子を伝えています。
-
別荘文化のきっかけ
-
アレキサンダー・クロフト・ショーの貢献:
-
1886年(明治19年)、カナダ出身の宣教師アレキサンダー・クロフト・ショーが軽井沢を訪れ、標高約1000mの高原地帯の清涼な気候と美しい自然に魅了されました。彼は家族や友人に軽井沢を避暑地として推奨し、1888年(明治21年)に旧軽井沢の大塚山に簡素な別荘を建てました。これが軽井沢の別荘文化の始まりとされています。
-
ショーは軽井沢を「保健と勉学の適地」として内外の知名人に紹介し、宣教師仲間を中心に別荘建設が広まりました。1893年(明治26年)には日本人の別荘も初めて建てられました。
-
ショー以前にも、1875年に測量師コリン・マクヴェインや1883年にドイツ人医師ジッセ・ラトゲン、1881年にイギリス人外交官アーネスト・サトウが軽井沢を訪れ、その魅力を記録していましたが、ショーの影響が決定的でした。
-
-
雨宮敬次郎の植林:
-
明治時代初期、軽井沢は浅間山の噴火による火山灰で荒廃した高原でした。実業家雨宮敬次郎がカラマツ約700万本を植林し、現在の軽井沢の森の基礎を作りました。この緑豊かな環境が、別荘地としての魅力を高めました。
-
-
インフラの発展:
-
1890年代以降、軽井沢は外国人宣教師や富裕層の避暑地として発展。1894年に軽井沢ホテル(現存せず)、1900年代には万平ホテルやつるや旅館が開業し、滞在インフラが整いました。
-
1910年代には鉄道(現在のしなの鉄道やJR北陸新幹線)の整備が進み、アクセスが向上。東京からの避暑客が増え、別荘地としての地位が確立されました。
-
-
自然保護と条例:
-
軽井沢の別荘文化が100年以上続く要因の一つは、町の「自然保護対策要項」です。土地分筆は1000㎡以上、建ぺい率・容積率は20%以内、建物は2階建てまでという厳しいルールが景観を保ち、別荘地としての価値を維持しています。
-
文学者の住まいと軽井沢
軽井沢は、明治末期から大正・昭和にかけて多くの文学者が訪れ、別荘や旅館に滞在し、創作活動を行いました。清涼な気候と国際的な雰囲気が文学者を惹きつけ、独特の文学的風土を育みました。以下に代表的な文学者とその住まいを紹介します。
-
初期の文学者(明治期):
-
森鴎外や正岡子規は、徒歩や馬車鉄道で碓氷峠を越えて軽井沢を訪れ、印象記を残しました。鴎外は自然の美しさを、子規は俳句に詠みました。
-
これらの文学者は主に旅館や知人の別荘に滞在し、長期定住は少なかった。
-
-
大正時代の文学者:
-
夏目漱石(1912年)、有島武郎(1916年)、室生犀星(1920年)らが軽井沢を訪れました。有島武郎は別荘を所有し、軽井沢を舞台にした作品を執筆。 与謝野鉄幹・晶子夫妻は、つるや旅館や貸別荘に滞在し、軽井沢の自然を歌に詠みました。晶子の歌集には軽井沢の情景が数多く登場します。
正宗白鳥や萩原朔太郎も軽井沢ホテルや三笠ホテルに滞在し、創作のインスピレーションを得ました。
-
-
昭和時代の文学者:
-
堀辰雄は軽井沢に深く縁があり、星野温泉や貸別荘に滞在。代表作『風立ちぬ』は軽井沢の風景や気候を背景に描かれました。堀の記念碑が町内に残っています。
-
芥川龍之介、谷崎潤一郎、島崎藤村も軽井沢を訪れ、万平ホテルや油屋旅館に滞在。藤村は追分宿近くに縁があり、詩や小説に軽井沢の情景を反映しました。
-
北原白秋や若山牧水は、軽井沢のカラマツや浅間山を詩や短歌に詠み、記念碑が建立されています。
-
-
文学碑と記念館:
-
軽井沢には文学者ゆかりの記念碑や銅像が点在します。例えば、旧碓氷峠見晴台には『万葉集』の碓氷峠の歌碑(1967年建立)があり、古代の旅情を伝えています。
-
堀辰雄や与謝野晶子の記念碑も観光スポットとして知られ、文学散策が楽しめます。
-
-
文学者の住まいの特徴:
-
文学者は、軽井沢ホテル、万平ホテル、つるや旅館、星野温泉、油屋旅館などの老舗宿に滞在するか、貸別荘を借りて夏を過ごしました。一部の文学者(有島武郎や山本鼎)は自らの別荘を所有し、長期滞在しました。
-
軽井沢のサロン的な雰囲気や国際的な避暑地の空気が、文学者たちの交流や創作を刺激。多くの作品に軽井沢の清涼な空気や自然が反映されています。
-
まとめ
-
軽井沢宿の歴史:江戸時代の中山道の要衝として栄えたが、明治以降は交通の変化で衰退。浅間山の噴火など自然災害も影響した。
-
別荘文化のきっかけ:1886年のショーの訪問と別荘建設、雨宮の植林、インフラ整備が軽井沢を避暑地に変えた。自然保護条例が景観を維持。
-
文学者の住まい:明治末期から昭和にかけて、森鴎外、夏目漱石、堀辰雄らが軽井沢の旅館や別荘に滞在し、自然や気候を作品に反映。記念碑や史跡が文学的風土を今に伝える。