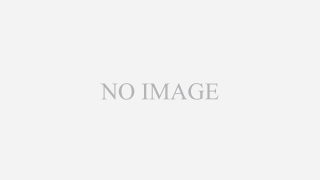人口減に合わせて政治家や役人は減っているのか?
大企業の縮小や子会社の吸収は、人口減や市場縮小に対応した効率化の一環として見られますね。
実際に、日本では少子高齢化による労働力不足や需要減で、企業が事業再編や統合を進めるケースが増えています。
例えば、2020年代に入ってからも、大手企業が子会社を吸収合併したり、非中核事業を売却する動きが活発です(具体例はWeb検索で最新のM&A動向を参照可能)。
一方、政治家や官僚、学者の数はどうか。
日本の国会議員は衆参合わせて約710人で、人口比で見ると諸外国(例:米国の議員数は約535人)と大差ないものの、人口減に比例した削減は進んでいません。
地方議員も約3万人(2023年時点)で、自治体統合が進む中でも大幅削減は議論段階にとどまります。
官僚(国家公務員)は約33万人(2023年、一般職)で、デジタル化や業務効率化で一部削減の動きはあるものの、人口減に追随する規模ではない。
学者も、大学教員数は約18万人(2022年)で、学生数減少に伴う大学再編は進むが、教員数の削減は緩やかです。
増税について、2023年度の税収は約71兆円(過去最高)だが、歳出も約114兆円と膨張。
社会保障費(約35兆円)が主な増税要因で、人口減でも高齢者向け支出が増えるため、効率性は確かに課題。政治家や官僚が「何も産まない」という批判は、生産性が見えにくい行政サービスの評価が難しい点に起因します。
ただし、行政のデジタル化や規制緩和で効率化を図る動きは一部進んでいます(例:デジタル庁の取り組み)。
非効率さの指摘はもっともですが、行政や学術の役割は直接的な「生産」より、インフラ整備や知識創出にあるため、
一概に削減が正解とも言えません。
とはいえ、人口減下でのリソース配分の最適化は、どのセクターでも喫緊の課題ですね。