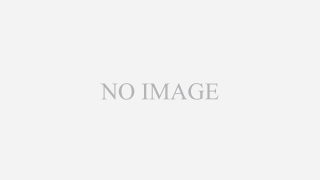貸家からの退去の費用精算の少額訴訟の方法
1 請求内容の整理
-
-
請求する金額(60万円以下)と理由(例:未払い代金、貸したお金の返済など)を明確にします。
-
2 訴状の作成・提出
-
簡易裁判所の窓口またはオンラインで訴状の書式を入手。
-
訴状に原告(あなた)と被告(相手)の情報、請求の理由、金額、証拠を記載。
-
裁判所に訴状を提出し、手数料(請求額に応じた印紙代)を支払います。
3 裁判の準備
-
裁判所から期日が通知されます(通常1回の審理で終了)。
-
証拠や主張を整理し、簡潔に説明できるように準備。
4 審理
5 判決・執行
ポイント:
-
弁護士は不要な場合が多いですが、複雑な場合は相談も検討。
-
手続きは簡易で1~2か月で終わるケースが多い。
東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(通称「東京ルール」)
1. 原状回復の基本原則
-
原状回復の定義:賃借人が借りた当時の状態に戻すこと。ただし、経年劣化や通常の使用による損耗(例:壁の日焼け、家具の設置跡)は対象外で、貸主(大家)が負担する。
-
賃借人の負担:故意・過失による損傷(例:タバコのヤニ汚れ、飲み物をこぼしたカーペットのシミ、ペットの爪痕など)は賃借人が修理費用を負担。
-
契約の優先:契約書に特別な条項がある場合(例:退去時に必ずクリーニング費用を負担するなど)、そちらが優先される。
2. 敷金精算の流れ
-
退去時検査:退去時に大家や不動産業者と一緒に部屋の状態を確認。入居時のチェックリストや写真と比較し、損傷の責任を明確化。検査は通常20~40分程度。
-
クリーニング費用:基本的なクリーニング費用(1㎡あたり1,000~2,000円+税)は大家が負担するが、契約で「賃借人負担」と明記されている場合、敷金から差し引かれることが一般的。
-
見積もりと返金:修繕・クリーニング費用の見積もりが退去後1~2か月で提示され、敷金から差し引かれた残額が返金される。見積もりに不満がある場合、修正を依頼可能。
3. 東京ルールの特徴
-
明確な負担区分:ガイドラインには、どの損傷が大家・賃借人の負担か具体例が図解で示されている(例:壁のピンの穴は賃借人負担、経年による壁紙の変色は大家負担)。
-
トラブル防止:入居時・退去時のチェックリスト作成や写真撮影を推奨し、証拠を残すことで不当な請求を防ぐ。
-
条例の背景:2004年に東京都が賃貸住宅紛争防止条例を制定し、敷金返還や高額請求のトラブルを減らす目的でガイドラインを公開。
4. 実践的なアドバイス
-
入居時の準備:入居時に部屋の状態を写真やチェックリストで記録。
-
契約確認:契約書にクリーニング費用や原状回復の特約があるか確認。特約がある場合、それがガイドラインに反しないかチェック。
-
不当請求への対応:高額な請求を受けた場合、ガイドラインを参照し、項目ごとの明細を要求。必要なら弁護士や東京都の住宅政策課に相談(日本語のみ)。
参考資料
-
ガイドラインは東京都住宅政策本部のウェブサイト(https://www.metro.tokyo.lg.jp)で無料ダウンロード可能(英語版もあり)。
-
詳細な相談は、東京都住宅政策課(日本語のみ)や弁護士に。