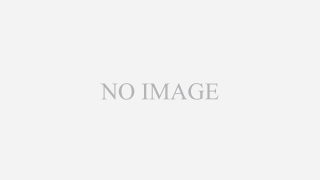複雑で曖昧な問題に対処するKJ法
KJ法(川喜多式カード法)は、社会人類学者である川喜田二郎博士によって開発された問題解決やアイデア発想のための手法です。1951年にフィールドワークの経験をもとに考案され、その後、日本のビジネス界や教育現場などで広く活用されています。
KJ法の基本的な概要
KJ法は、情報を収集・整理し、それをもとに新しい洞察や解決策を見出すことを目的とした方法です。特に、複雑で曖昧な問題に対処する際に効果的とされています。この手法の特徴は、「カード」を用いて情報を視覚的に整理しながら考える点です。
KJ法の手順
1. データを収集する
問題解決に関連する情報や意見を集めます。この情報は、自分の考えやチームメンバーのアイデア、資料からのデータなど、幅広い視点を含めることが重要です。
2. 情報をカードに記録する
各情報やアイデアを1枚のカードに記入します。カードには1つの情報や意見だけを記載し、短く具体的に表現することが求められます。
3. カードをグループ化する
すべてのカードを一度机の上に広げ、関連性のあるもの同士をグループ化します。この際、「何が関連しているか」を直感的に判断し、考えすぎないように進めることがポイントです。
4. グループに名前を付ける
それぞれのグループに適切なラベルやタイトルを付けます。このラベルは、グループ内の情報の共通点やテーマを簡潔に表現したものです。
5. グループの関係を図式化する
グループ間の関係性を図式化します。矢印や線を使って、全体の構造や流れを視覚的に示します。これにより、問題全体の俯瞰図が得られます。
6. 解釈や洞察を導く
図式化した情報をもとに、解決策や新しいアイデアを考えます。この段階では、分析結果を文章化したり、具体的なアクションプランを立てたりします。
KJ法の特徴とメリット
- 視覚的な整理: カードや図式を使うことで、情報を直感的に理解できる。
- チームワークに適している: 複数人で取り組む際に、全員の意見を取り入れやすい。
- 複雑な問題の整理に強い: 混沌とした情報を整理し、新しい発想を得られる。
KJ法の具体的な活用例
- 新商品開発: 顧客のニーズや市場のトレンドを整理してアイデアを生み出す。
- プロジェクトの問題解決: 発生している問題を分解して原因を特定し、解決策を考える。
- 学術研究: フィールドワークなどで収集した膨大なデータを分析し、結論を導く。
KJ法はシンプルながらも奥深い方法であり、個人やチームでの創造的な問題解決に非常に有用です。また、ビジネスだけでなく、教育や研究分野でも活用できる汎用性の高さが魅力です。
テルはリハウスで活用しました。