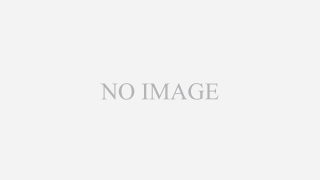新自由主義の終焉
 新自由主義の終焉
新自由主義の終焉
新自由主義の終焉
1. 新自由主義の終焉とグローバリズムへの反発
- 新自由主義は格差拡大や中間層の没落を招いた。
- 欧米での産業空洞化・移民問題がナショナリズムを刺激。
- 2025年以降、保護主義が主流となり、自由貿易や国際機関の影響力が低下。
- ポピュリズム・ナショナリスト政党が台頭、グローバル企業の行動が制限される。
- 「選択的グローバリズム」が現れる可能性が高い。
2. アメリカの対中戦略と日本の役割
- 米中対立は貿易・技術・軍事の分野で継続。
- 中国は経済減速・人口問題など内的課題を抱える。
- アメリカは同盟国との連携を強化して中国をけん制。
- 日本は半導体・AIなど先端分野で重要な役割。
- 地理・歴史的に中国を抑える拠点としても注目される。
3. 日本の次の30年と「勝てる席」
- 成功要因:
- 技術覇権:官民連携による半導体・AI強化。
- エネルギー安全保障:再エネ・原子力活用で自給率向上。
- 外交的多様性:インド・ASEAN・EUとの連携強化。
- 人口問題対応:移民受け入れ、女性活躍、生産性改善。
- 中立・信頼される立場を活かせば国際的に有利。
4. 新しい世界秩序の特徴
- ナショナリズム:移民制限・産業保護が進展。
- 保護主義:補助金や関税による国内優先。
- 孤立主義:国際協調より自国重視、ミニラテラリズムが中心。
- ブロック化:米中軸に三極構造(自由・権威・非同盟)。
- 国連などの影響力低下、G7やQUADが連携の中心に。
5. リスクと不確実性
- 経済的:成長鈍化・インフレリスク。
- 軍事的:米中間の偶発的衝突の可能性。
- 技術的:技術標準やインターネットの分断。
- 社会的:国内分裂・マイノリティ抑圧の懸念。
結論
- 2025年は新自由主義から新秩序への転換点。
- 分断と競争が進む中で、日本には柔軟な外交と内政改革が必要。
- 短期はナショナリズム・保護主義が支配的だが、長期的には協調体制の構築が課題。
- これは一つのシナリオだが、現実的な延長線上にある。