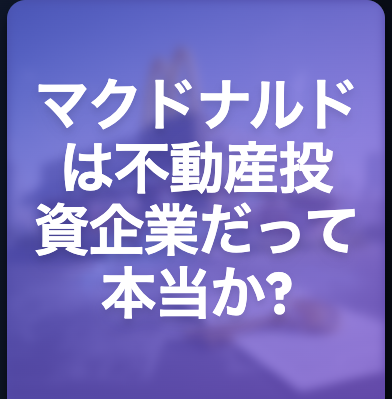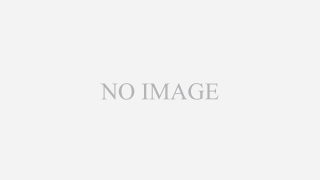日本版ライドシェア(正式名称:自家用車活用事業)とは?
日本版ライドシェア(正式名称:自家用車活用事業)は、一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を運ぶサービスです。2024年4月から開始され、タクシー不足を補う目的で導入されました。海外のライドシェア(Uberなど)と異なり、以下のような特徴があります:
-
運営主体:国土交通省から営業許可を受けたタクシー事業者が運行管理を担当。
-
対象地域:タクシー不足が顕著な地域(例:東京23区、横浜市、名古屋市、京都市など)で、特定の曜日や時間帯に限定。
-
ドライバー:普通自動車免許(取得後1年以上)を持つ一般ドライバーで、第二種免許は不要。タクシー事業者による研修が必要。
-
料金:タクシーと同じ料金体系で、ダイナミックプライシング(需要に応じた変動料金)は採用せず、予約時に料金確定。
-
利用方法:主に配車アプリ(例:GO、Uber、DiDi、S.RIDE)で予約・キャッシュレス決済。一部地域では電話予約も可能。
-
目的:タクシー不足や交通空白地の解消、観光需要への対応。
2025年4月時点で全国47都道府県、900以上のタクシー会社が参入していますが、地方(例:松山市、富山)では利用が少なく、運行回数は1時間あたり0.1~0.3回程度。一方、都市部(東京、札幌、名古屋)では1.5~1.7回と利用が進んでいます。課題として、ドライバー確保の難しさや認知度の低さ、厳しい運行時間・台数制限が挙げられ、規制緩和の議論が続いています。
万博の試行は不調のようです。