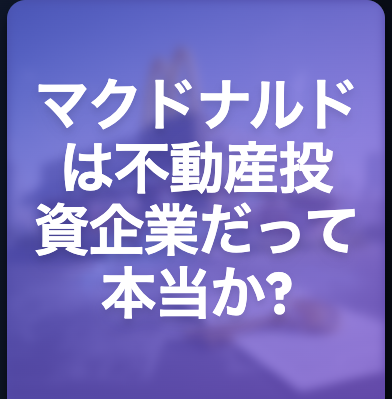コンパクトシティ化
コンパクトシティ化は、都市の持続可能性と生活の質を向上させるための都市計画の概念です。以下にコンパクトシティ化について詳しく説明します。
定義と基本概念
コンパクトシティとは、都市的土地利用の郊外への拡大を抑制し、中心市街地の活性化を図りながら、生活に必要な諸機能を近接させた効率的で持続可能な都市を目指す概念です1。この概念は、1973年にジョージ・ダンツィヒとトーマス・L・サーティによって提唱されました。
主な特徴は以下の通りです:
- 高密度で近接した開発形態
- 公共交通機関でつながった市街地
- 地域のサービスや職場までの移動のしやすさ
コンパクトシティ化の目的
コンパクトシティ化は以下の目的を達成しようとしています:
- 生活サービス機能の維持と住民の健康増進
- サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化
- 行政サービスの効率化と行政コストの削減
- 地域経済の活性化
- エネルギー効率の向上と低炭素社会の実現
コンパクトシティの類型
コンパクトシティには主に以下の類型があります:
- 多極ネットワーク型: 生活サービスを提供するエリアと居住者を誘導し人口密度を保ったエリアを設定し、エリア間を公共交通機関で結ぶタイプ。
- 串と団子型: 鉄道など公共交通機関を発展させ、その沿線に居住エリア、商業エリア、行政エリア、文化施設エリアなどの機能を集めるタイプ。
メリット
コンパクトシティ化には以下のようなメリットがあります:
- 自家用車を持たない人でも公共交通機関や徒歩で施設を利用できる
- 社会インフラの維持管理費用の削減
- 環境負荷の軽減
- 経済交流とコミュニティの活性化
- 農地や緑地の保全
- 健康増進の期待
デメリット
一方で、以下のようなデメリットも考えられます:
- 集約された居住エリアへの転居を希望しない住民の存在
- 居住エリアの高密度化による住民同士のトラブル発生の可能性
日本におけるコンパクトシティ政策
日本では、2014年に「コンパクトシティ法」(改正都市再生特別措置法)が施行され、コンパクトシティが国策として位置づけられました1。この法律により、自治体は立地適正化計画を策定し、居住誘導区域と都市機能誘導区域を設定することで効率的な街づくりを行うことができるようになりました。
2024年3月31日現在、747都市が立地適正化計画に関する具体的な取り組みを行っており、うち568都市が立地適正化計画を作成し公表しています。
結論
コンパクトシティ化は、少子高齢化と人口減少に直面する日本の自治体にとって重要な施策となっています。生活利便性の維持、経済活動の活性化、環境負荷の軽減など、多くのメリットが期待されています。しかし、実施にあたっては地域の特性や住民のニーズを十分に考慮し、バランスの取れた都市計画を進めることが重要です。