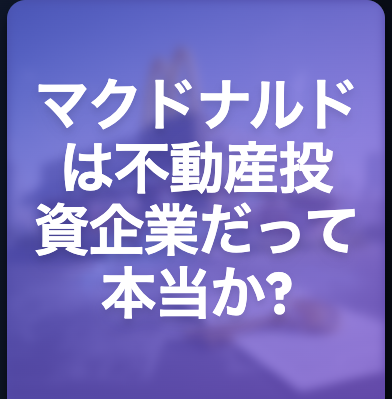2026年以降に予想される上がる負担
「今後の費用負担」は、日本の財政健全化、社会保障制度の持続性確保、そして少子化対策を目的とした増税や負担増の議論を示しています。
1. 年金保険料の負担増(第3号被保険者制度の見直し)
専業主婦(第3号被保険者)への優遇措置を見直し、負担増を求める動きですが、これは「年金制度の公平性」と「専業主婦世帯の経済的負担増加」のバランスが問題になります。共働き世帯が増える中、第3号被保険者制度の見直しは合理的な側面もありますが、専業主婦世帯の家計には大きな影響を与えるでしょう。
2・ 通勤手当に対する課税
現在は15万円まで非課税となっている通勤手当に課税する案は、サラリーマンの可処分所得を減少させるため、特に都市部の通勤者にとっては負担増となります。一方で、リモートワークの普及を促す効果も考えられます。ただし、企業側の経費増を招き、結果として給与減少や雇用調整に繋がる可能性もあります。
3. 退職金への課税強化
現状では退職金の課税は優遇されていますが、これは長年勤続した人の老後資金を守るための措置です。もし課税強化が進めば、老後資金の形成に影響を与える可能性があり、結果として年金への依存度が高まるという逆効果も考えられます。
4. 走行距離税(EV普及による新たな財源)
EVの普及によるガソリン税収の減少を補うための施策ですが、これにより「移動コストの上昇」「地方在住者への負担増」が問題視される可能性があります。都市部と地方で負担の偏りが出るため、慎重な設計が求められます。
5. 所得税の増税(防衛増税)
防衛費の増額を目的とした所得税の増税ですが、国民負担の公平性の観点から議論が必要です。特に、現在の経済状況を考えると、増税による景気への悪影響も考慮しなければなりません。
6. たばこ税の増税
たばこ税は増税しやすい税目の一つですが、すでに高額となっているため、さらなる増税が禁煙促進にどこまで寄与するかは不透明です。また、加熱式たばこへの増税は、従来の紙巻きたばことの差が縮まり、消費行動にどのような影響を与えるかが注目されます。
7. 子育て支援金(いわゆる独身税)
少子化対策の財源確保として検討されていますが、「独身者への不公平感」が大きな問題になります。少子化対策としての実効性がどこまであるか疑問が残るうえ、単身者や子供のいない夫婦にとっては新たな負担となり、不満が強まる可能性が高いでしょう。
総評
これらの施策は、財政健全化や社会保障の持続可能性を目指すものの、国民の可処分所得の減少、企業負担の増加、景気への悪影響といった懸念が多く含まれています。特に、退職金課税や通勤手当課税のように、「中間層・サラリーマン層」への負担が集中しやすい点が問題となるでしょう。
政府が進める税制改革は、単なる財源確保だけでなく、国民の生活や経済成長とのバランスを考えた制度設計が求められます。